「子供が生まれたらイクメンになるぞ!」初めての出産を控えたパパの中には、こう決意している方も多いでしょう。
ただ「イクメンって何するの?」と聞かれたら、あなたはどう答えるでしょうか?漠然と家事・育児を手伝うイメージしかないのではないでしょうか。
以下の画像を見てください。Googleで「イクメン + スペース」を入力した結果ですが、関連ワードにネガティブな言葉が多いことがわかりますよね。(InPrivateモードで検索したので、私の検索履歴は無関係です)。つまり、いいイメージを持たれがちな「イクメン」が、実際はそうではないということがうかがえます。

なぜこのような結果になるのでしょうか?これは、男性が考える「イクメン」像が、女性が考える「イクメン」像とかけ離れていることから生じていると思われます。
「イクメン」になろうという決意、空回りさせたくはないですよね?そこでこの記事では「自称イクメン」と揶揄される人の特徴を紹介しつつ、そうならないためにパパが産前からやっておくべきことをまとめました。きっと役立つ情報があるので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
そもそもイクメンとは

イクメンという言葉が使われ出したのはいつ頃からでしょうか?
コトバンクでは以下のように記載されています。
2007年(平成19)ごろから女性誌や育児雑誌にイクメンをテーマにしたウェブサイトや男性の子育てを扱った記事が頻繁に掲載されるようになった。当初は育児休業基本給付金などの制度を利用して育児休暇(育休)を申請した男性や子育てを趣味にする男性に限って使われることが多い呼称であった。その後、若い父親の育児が社会に浸透するにつれ、子育てする男性すべてを表す意味でも使われるようになった。
イクメンとは – コトバンク (kotobank.jp)
背景として当時はまだ男性で育休を取得する人が稀であったため、取得しない人と区別しやすいようにメディアが名付けたのが「イクメン」の発端です。
しかしイクメンという言葉がどんどん美化されてきた昨今、実はイクメンという言葉自体が疑問視されています。以下はTwitterでの呟きです。
前にも呟いたけど、自分の子供を育ててなにが「イクメン 」だよ。
— ヒロム(結婚しても片想い) (@jHBdMyw6TgkEwDX) August 21, 2018
「俺イクメンなんです」なんて「俺二足歩行なんです」と一緒だからな。
フライデー記事にもお褒めの言葉を書いていただいて嬉しいですが、イクメンという言葉は、やはりあまり好きではないな😭イクメンと呼ばれて嬉しくは無いし、父親としてやるべき当たり前のことしかしてないのでモヤモヤします。男がしたら褒められるような事なんて、世の中に一つも無くなれば良いのにね
— ryuchell (@RYUZi33WORLD929) September 19, 2020
そもそもイクメンという言葉自体が日本特有のものなので、海外の人にイクメンについて説明したところ「それ普通の”父親”じゃね?」みたいに返されたというツイートもありました。
「イクメン」とは称号ではなく、メディアでわかりやすく伝えるために生み出された記号だと思ってください。
自称イクメンとは

イクメンについては先述した通りですが、残念ながら世の中には自分がイクメンだということを過剰にアピールしつつ全く出来ていない「自称イクメン」が後を絶ちません。
SNSを見ると大量の自称イクメンを揶揄する投稿が見られます。それらを全てまとめているとキリがないですが、主に以下のような特徴があります。
- 育児も家事もしていると自画自賛している
- 家事はやらない。やっても中途半端
- 簡単な育児しかしない
- 予防接種などのイベントには無関心
なぜこういう風になってしまうのでしょうか?私はパパの「圧倒的な当事者意識不足」が原因だと思います。
育児はママがメインでやるもの、パパはそれを補助する。こういった「育児を手伝っている」という意識が、自称イクメンが嫌われている要因ではないでしょうか。
育児は手伝うものではありません。ママとパパは同じチームです。今から育児も家事も頑張ろうとしているパパは、ぜひ半面教師として上記の特徴を抑えておきましょう!
出産前のパパがやるべき8つのこと

夫がパパになるのはいつからでしょうか?それは「妻の妊娠がわかったとき」です。
そう、出産「後」ではなく出産「前」からパパとしての意識を変えていかないといけないのです!
ここでは私が実際に妻が妊娠中にやっていてよかったことを紹介します。どの家庭でも当てはまるようなことだと思うので、ぜひ参考にしてください。
- ママを労わる
- 色んな決め事をママに丸投げしない
- 会社に育休の交渉をする
- 会社で自分だけが抱えている仕事をなくす
- 楽をするための投資を惜しまない
- 各家庭にあった家事を覚える
- 両親学級に参加する
- 産後ケアの予約をする
ママを労わる
何よりも一番大事なことです。本当に大事なことです。
個人差はありますが、出産前のママはホルモンバランスの崩れや悪阻で心身共にボロボロです。体の不調ももちろんですが、「五体満足で子供が生まれるのか」「食事はどういうものを気を付ければいいのか」といった不安でいっぱいです。
パパも仕事で忙しいかと思いますが、出来る限りママを労わりましょう。ママが一日中寝ていてもそれは怠惰から来るものではありません。解決しようのないつらさを必死で耐えているのです。
悪阻がひどいときは食事もまともに取れない場合があります。ママの希望を聞いて、口に出来そうなものをそろえてあげるようにしましょう。
色んな決め事をママに丸投げしない
実は出産前から決めておくことが多くあります。一例をあげます。
- 産院選び
- ベビー用品の準備
- 陣痛タクシーの登録
- 産後の手続きの確認(出生届など)
これらのことをママ一人に全部お願いせず、夫婦で決めるようにしましょう。
出産には多くの選択と決定が発生します。それを一人で行うのは結構負担が大きいです。それが妊娠中のママともなれば余計にです。
色んな意思決定も夫婦でやれば乗り切れると思うので、しっかりと話しあうようにしましょう。
会社に育休の交渉をする
これは、絶対に必要です。パパは育休を取得しましょう。
一昔前までは男性の育休は非常に取得しづらい雰囲気がありましたが、近年は随分と改善されてきました。厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は12.65%(前年度7.48%)と大きく上昇していることがわかります。
そうは言ってもうちの職場は難しい…という方も安心してください。2022年秋から育児・介護休業法が改正され、企業は従業員に対して育休の取得意向を確認することが義務化されます。他にも育休を取得しやすい制度改正が行われているので、一度確認しておきましょう。
育休は最低でも1か月は取得するようにしましょう。社内での引継作業が必要になるので、育休の取得意思は早めに上司に相談できるとよいでしょう。
産後のママの体はボロボロです。出産での消耗はもちろん、体が元の状態に戻る産褥期と呼ばれる期間があります。個人差はありますが、この期間は産前には見られなかった様々な症状が起きます。ママの体を早く回復させてあげるためにも、しっかりと休息がとれる環境を作りましょう。
ちなみに私は最初育休は1か月で申請していましたが、出産後しばらくして「あ、これは足りないわ」と感じ3か月に延長させてもらいました。正直、1か月程度では赤ちゃんとの生活は安定しません…。
会社で自分だけが抱えている仕事をなくす
育休は労働者の権利ではありますが、だからといって仕事をないがしろにしてはいけません。あなたがいなくなることで回らなくなる仕事があると、会社側も育休取得に対して良い顔をしないでしょう。
例えば、あなただけが営業担当の顧客がいれば、サポートとして部下や同僚をつけるなどしてください。場合によっては上司にお願いするのもありでしょう。もし育休中に期限が来るようなタスクがある場合は、引き継ぎの準備も必要です。
今後のことも考えると、個人のタスクを共有・分担できるような組織が作れるとベストです。そうすれば、育休に関わらず急な体調不良による休暇も対応できるようになります。
あなたが上司なら自分で、そうでないなら上司にこのような組織作りを提案してみてはどうでしょうか。そのような環境作りをしておけば、今後部下たちも育休を取りやすくなるでしょう。
楽をするための投資を惜しまない
貯金に余裕がある場合は、家事を楽にするための家電の購入やサービス利用を惜しまないようにしましょう。
家電の中ではロボット掃除機の利用は特にオススメです。人がいない間に掃除してくれるので、家の中が常にキレイに保てます。それだけでなく、「どちらが掃除するか」という変な探り合いでストレスを感じることも減ります。
ただロボット掃除機を使ったことが無いと「使いこなせるかわからない」「本当に楽になるか疑問だ」と不安になりますよね。そういう方は家電レンタルがオススメです。モノカリを使えばルンバを始めとした最新家電をレンタルすることができるので、気になっている方は試してみてはいかがでしょうか。
各家庭にあった家事を覚える
もしパパが今まであまり家事をしていなくて、妊娠を機に家事を始めようとします。
家事を始めようとする心構えは素晴らしいです。ですが、ママに相談なく勝手に家事をするのはオススメできません。まずはママから家事の仕方を教えてもらいましょう。
家事は各家庭でやり方が微妙に異なるものです。もっといいやり方があったとしても、自己流で家事をするのはやめましょう。仕事でも同じですが、新参者が急に今までと違う仕事のやり方をするともやっとしますよね?もしやり方を変えたい場合は、事前にママに相談して実施することをオススメします。
両親学級に参加する
各自治体では初めての出産を控えるママとパパに向けて、知識や情報を共有してくれる両親学級というものが開催していることがあります。
出産後、ママは産院で赤ちゃんのお世話を一通り教えてもらえます。しかしパパは自分で調べるかママに教えてもらう必要があります。
出産前に予め正しい知識を身に着けるためにも、両親学級にはぜひ参加しましょう。沐浴の指導や、必要な情報が掲載されているハンドブックなどがもらえますよ。
産後ケアの予約をする
産後のママにとって、体がボロボロなのにすぐに始まる育児は不安がいっぱいです。そんなママの心身を回復させて、育児指導を行ってくれる産後ケアといったサービスがあります。
産後ケアにはいくつか種類があります。
- 病院や専用施設に入院する「入院型」
- 産後ケアを行っている施設に出向く「デイサービス型」
- ヘルパーさんに自宅に来てもらう「訪問型」
どれがいいかは家庭により異なるのですが、基本的にどれも事前予約が必要になります。産前は仮予約をして、産後に改めて本予約が必要になる場合もあります。パパが率先して調べて、ママの負担を少しでも和らげてあげましょう。
もちろんどれを選んでもそれなりの金額がかかります。ですが、産後すぐは慣れない育児に想像以上にストレスを感じます。個人的には何かしらの産後ケアを利用したほうがいいと思っています。
また住んでいる地区によっては補助金が出ることがあります。例えば東京都の該当地区だと、入院型のサービスで1泊あたり数万円の補助金が出ています。自分の住んでいる地区で産後ケア事業が行われていないか事前に調べておくと良いでしょう。
ちなみに我が家では訪問型の産後ヘルパーを1週間利用しました。興味がある方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
妊娠中から立派な「パパ」になろう

この記事では、パパが産前からやっておいたほうがいいことについて紹介しました。
「産前産後の恨み」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?たまひよの記事を見てもらえばわかると思いますが、パパは自覚なくママに負担をかけてしまっているときがあります。その恨みは根深く、熟年離婚の原因に繋がるともされています。
出産前、ママのお腹が大きくなっていることはわかりつつも、子供が生まれるということをパパは中々実感できないと思います。ですが出産に向けた準備をすることで、少しでも心の準備ができるのではないでしょうか。
かくいう私の子供もまだ0歳児。まだまだ育児は始まったばかりで、偉そうなことを言える立場ではありません。それでも私がやったこと・感じたことが、これからパパになる人に少しでも役立つものとなれば幸いです。一緒に良いパパになるために頑張りましょう!


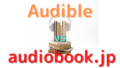
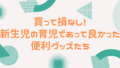
コメント